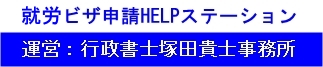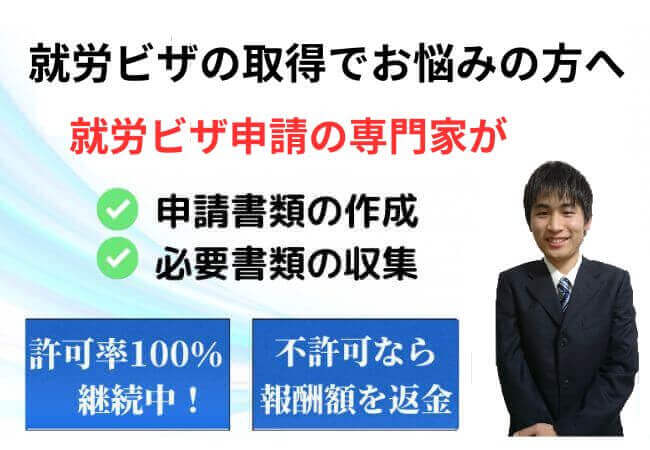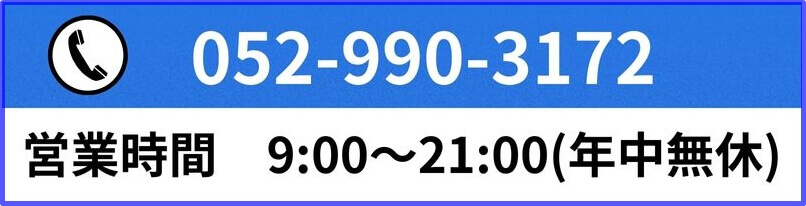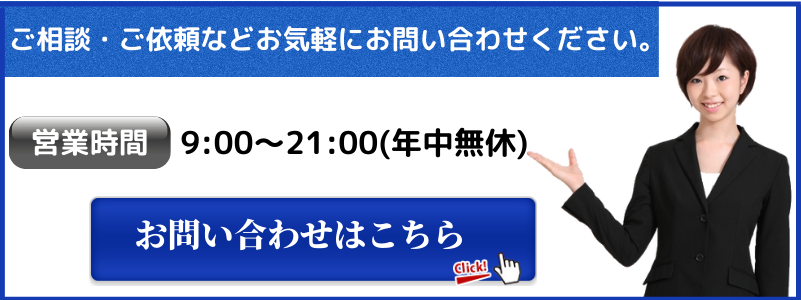【関市で就労ビザ取得をサポート】外国人雇用をご検討の企業・個人事業主の皆さまへ
岐阜県関市で外国人を採用し、就労ビザ(在留資格)の取得をお考えの方へ。
当事務所は、関市をはじめとした岐阜県エリアに対応した、就労ビザ申請の専門行政書士事務所です。
採用から申請、許可取得後のサポートまで、ワンストップで丁寧に対応いたします。
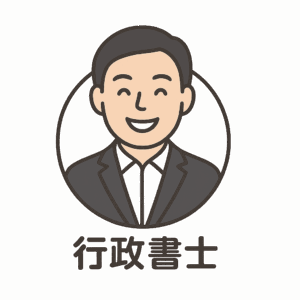
関市でこんなお悩みはありませんか?

- 外国人を雇いたいが、適切な在留資格がわからない
- ビザ申請の手続きが複雑で自信がない
- できる限り早く許可を取得したい
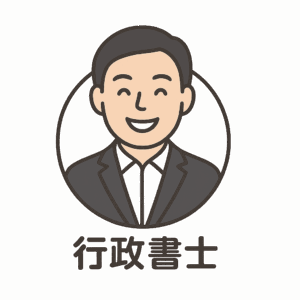
行政書士に依頼する4つのメリット
- 法令に準拠した正確な書類作成
- 岐阜出入国在留管理局への代理申請が可能
- 不許可リスクを軽減する徹底チェック体制
- 雇用条件と在留資格の整合性を的確に判断
関市で当事務所が選ばれる6つの理由
- 経験豊富な行政書士が一貫対応
- 書類作成〜提出まで完全代行で対応
- 心理カウンセラー資格保持者による安心のヒアリング
- 明朗な料金体系、追加費用なし
- 成功報酬+全額返金保証制度あり
- 土日・夜間の相談も可能(完全予約制)
▶︎ [料金・サービスの詳細はこちらへ]
関市での就労ビザ取得の流れ|外国人雇用をご検討の方へ

当事務所では、就労ビザの取得をスムーズに進めるため、5ステップのサポートをご提供しています。
STEP1|【初回相談無料】関市での就労ビザ相談受付中
電話またはWEBフォームから、いつでもお気軽にご連絡ください。
年中無休・即日対応も可能です。
📞 052-990-3172(受付時間:9:00〜21:00/年中無休)
📩 お問い合わせフォームはこちら(24時間受付中)
STEP2|Zoomによるオンライン面談対応
全国どこからでも対応可能なZoomによるオンライン面談に対応。
関市内の方も在宅でご相談いただけます。
STEP3|専門家が就労ビザの書類を正確に作成・チェック
出入国在留管理庁の審査基準に基づいた書類を、行政書士が正確に作成。
申請前に不備を徹底的に確認し、許可取得の成功率を高めます。
STEP4|申請はすべて代行対応
行政書士が岐阜出入国在留管理局へ代理申請を行います。
申請人本人の出頭は不要で、時間と手間を削減できます。
STEP5|在留カード取得後も関市で安心のアフターサポート
更新・永住・帰化申請まで、関市での外国人雇用を長期的に支援いたします。
【無料相談受付中】関市で就労ビザ申請をご検討中の方へ
- 外国人採用をスムーズに進めたい
- 在留資格に問題がないか確認したい
- ビザ申請を確実に進めたい
このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。
関市での就労ビザ取得を、行政書士が迅速かつ丁寧にサポートいたします。
お電話またはお問い合わせフォームからいつでもご連絡いただけます。
記事の監修者
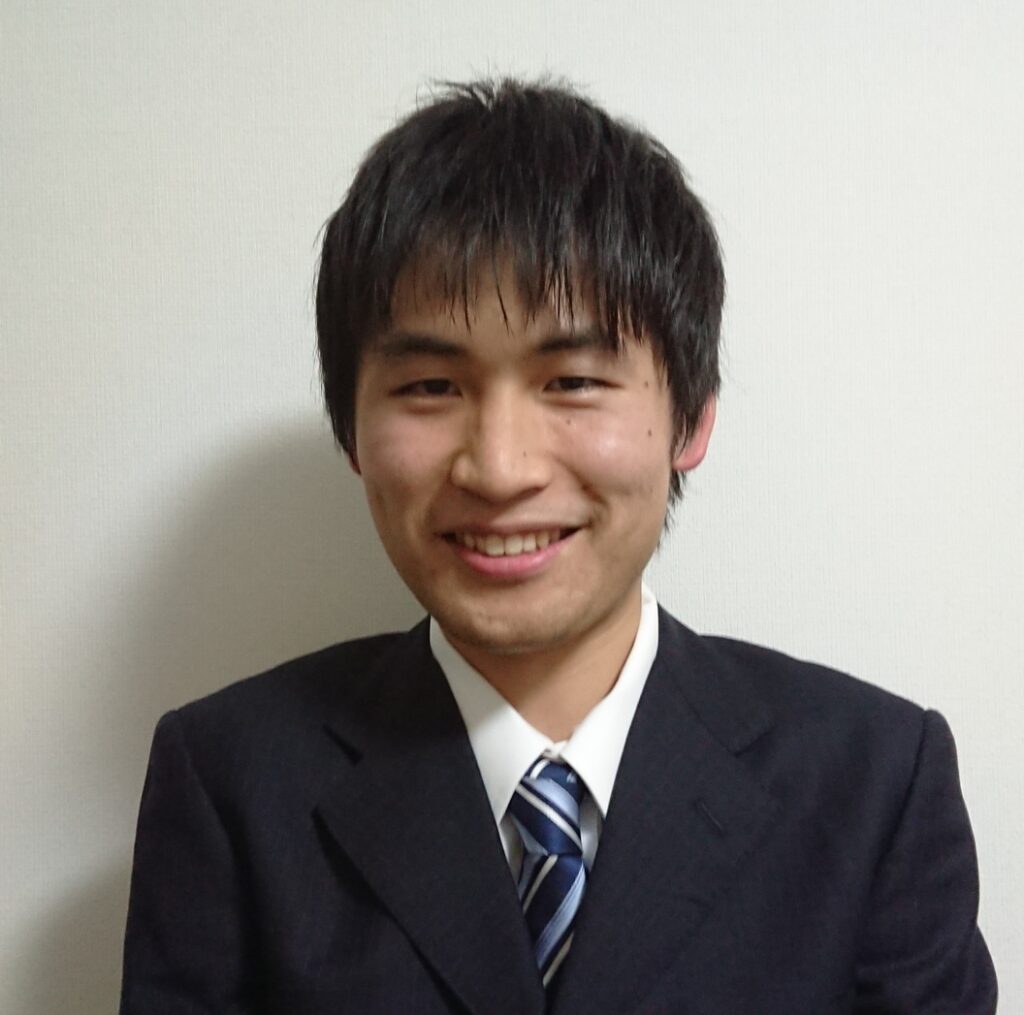 行政書士塚田貴士事務所
行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
岐阜県関市の特徴
岐阜県関市における外国人労働者は、主に製造業を中心に就労しており、地域のものづくり産業を支える重要な人材となっています。
特に関市は刃物の産地として知られており、金属加工や機械組立といった分野で技能実習生や特定技能の外国人が多数活躍しています。
業種としては、旋盤加工・溶接・プレス作業・電子部品の組立などが多く、専門的な技術を持った人材も増えてきています。
出身国はベトナムをはじめ、フィリピンやブラジル、中国などが中心です。ブラジルやフィリピン出身の定住者も多く、家族とともに長期的に関市に暮らす外国人も見られます。
また、市内では多言語対応の相談窓口や生活支援制度も整備されており、安心して働きながら生活できる環境が徐々に整っています。
一方で、日本語によるコミュニケーションや文化の違いに対する理解が課題とされており、企業や行政による語学支援や職場研修の充実が求められています。
今後は、より高度な技能を持つ外国人材の受け入れと定着支援が、地域経済と共生社会の持続に向けて重要になっていくでしょう。